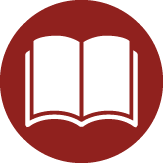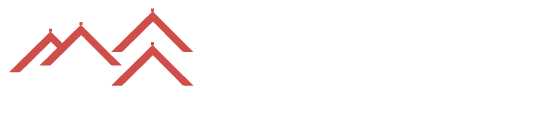沖縄返還交渉と核戦略
文書情報
|
 |
1969年6月、ワシントンで沖縄返還の日米交渉が正式に始まり、11月の日米首脳会談での両3年以内に返還の時期について決定することが合意され、沖縄返還は現実のものとなりました。
紹介する文書は、1969年7月3日付の NSC Under Secretaries Committee (国家安全保障会議 次官委員会)で、エリオット・リチャードソン委員長から、国防総省次官、国家安全保障担当大統領補佐官、CIA長官、統合参謀本部長に宛てた「Okinawa Negotiating Strategy(沖縄交渉戦略)」と題したトップシークレット扱いの文書です。
この文書(7枚)の中から注目される部分を和訳して紹介します。
「沖縄返還交渉の基本戦略」では、この委員会の目標を「沖縄に関する核(兵器)、通常(兵器)ほかを含む米軍の権限について、同年11月の佐藤・ニクソン会談で日本政府から合意を得ること」、「現段階で日本政府は、米国政府の要求をより良く理解している」とし、日米両者の交渉カードについてが次のことが書かれています。
《米国政府側の有利な交渉カード》
・「日本政府は、米国政府との深刻な摩擦を起こすようなところまで、(沖縄)返還交渉を推し進める気はないようだ」
・「日本国民にほぼ受け入れられる条件での返還は、保守派、特に佐藤派にとって政治的に有利となるだろう」
・「交渉のさらに後の段階で核兵器撤去の可能性を検討するという我々の意欲(日本側は明確な示唆を示している)は、交渉においてかなり優位な力となる」
《日本政府側の有利な交渉カード》
・「現在、アジア地域で唯一の非共産主義主要国である日本との同盟関係の維持を米国政府が強く望んでいること」
・「安全保障上の必要性と責任に応じるために米国政府が沖縄に基地を保有する権利を求めていること」
・「米国政府も理解しているように、沖縄返還を求める圧力が日本と沖縄で高まり、注意深くそれに対処しなければならないこと」
また、「従来の自由使用に関する主要な課題」では、「米国政府の目的は、特に韓国、台湾、ベトナムに関して、沖縄の基地を最大限これまで通り自由に使用すること」とあり、「 核兵器に関する権利」では、次のことが書かれています。
・「日本人は核兵器に強く反対するという厳しい世論があるが、返還後の沖縄への核兵器配備についてはほとんど何も言わない。
・我々は、核兵器が重要な軍事力であり大きな抑止力を持つという我々の考えを日本人に思い起こさせ続けるべきである。
・(沖縄での)核兵器の継続的配備の意義を、従来通りの自由使用に関する交渉で優位に立つために、我々は利用すべきである。
・もし核兵器配備という米国政府の考えを撤回しないのであれば、その緊急配備、つまり緊急事態の際は沖縄に核兵器を配備する権利を得ることに力を注ぐべきである。
・問題は、両国政府がどんな状況を緊急事態であると決定するか、決定された場合は米国政府が必要な装備を、さらなる相談なく、日本に配備できるか、である。
さらに、「その他事項」では、以下の内容が書かれています。
・日本政府は沖縄の防衛責任を引き受けること。沖縄の危機的状況においては、統合司令部設置の可能性を検討する必要があること。
・米国政府が沖縄の核兵器撤去に合意した場合、撤去費用(5000万ドル)を日本政府負担に求める可能性があること。返還に伴う他の撤去費用も日本政府に負担を求める可能性もあること。
・沖縄のボイスオブアメリカ(VOA)と外国放送情報局(FBIS)の継続使用を求めること。
このように、沖縄の核に関する米国の交渉戦略の思惑がこの文書から見えます。